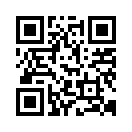2015年12月09日
あんこの聖地「小城」にて。
がきたかです。
今日は朝から小城(三日月?)にて仕事だったので、佐賀であんこの聖地、羊羹で有名な小城の街中に立ち寄った。
で、このブログをやってたら一度は行きたいと思っていた「村岡総本舗羊羹資料館」へ寄ってみた。

羊羹の歴史や原料、パッケージ、道具など、様々なものが展示されていた。



また、小城羊羹や村岡総本舗の歴史などを映像で見れたり、無料で抹茶と羊羹を振舞ってもらい、教養を深める良い時間を過ごさせてもらった。

で、ビデオを見ながら羊羹と抹茶を頂いていると、同店の副社長がやってきて、羊羹の歴史や、昔にあった羊羹に関するエピソードや、海外での羊羹に対する反響などを色々とご説明いただいた上に、私からの素人みたいな質問にも丁寧にご回答いただけて、有意義な時間を過ごすことご出来た。
ただ、今日聞いた情報ですと、小城で小城羊羹を売っている店舗が、現在25店舗もあるとのこと。。
また、同店だけでも店内を見ると羊羹も何種類もあるし、羊羹以外もあるし、しかも1本5,000円もする羊羹など、かなり財布に厳しい企画であることが垣間見れた。
全部制覇の目論みは・・・といった感じ。
購入した、羊羹については、また後ほど投稿します。
今日は朝から小城(三日月?)にて仕事だったので、佐賀であんこの聖地、羊羹で有名な小城の街中に立ち寄った。
で、このブログをやってたら一度は行きたいと思っていた「村岡総本舗羊羹資料館」へ寄ってみた。

羊羹の歴史や原料、パッケージ、道具など、様々なものが展示されていた。



また、小城羊羹や村岡総本舗の歴史などを映像で見れたり、無料で抹茶と羊羹を振舞ってもらい、教養を深める良い時間を過ごさせてもらった。

で、ビデオを見ながら羊羹と抹茶を頂いていると、同店の副社長がやってきて、羊羹の歴史や、昔にあった羊羹に関するエピソードや、海外での羊羹に対する反響などを色々とご説明いただいた上に、私からの素人みたいな質問にも丁寧にご回答いただけて、有意義な時間を過ごすことご出来た。
ただ、今日聞いた情報ですと、小城で小城羊羹を売っている店舗が、現在25店舗もあるとのこと。。
また、同店だけでも店内を見ると羊羹も何種類もあるし、羊羹以外もあるし、しかも1本5,000円もする羊羹など、かなり財布に厳しい企画であることが垣間見れた。
全部制覇の目論みは・・・といった感じ。
購入した、羊羹については、また後ほど投稿します。
2015年11月13日
【見学レポート】コーヒーようかん(やつだ屋)<2>
昨日の投稿のつづきです。

↑あんを入れた直後はこんな感じですが、

煮込みながら混ぜていくと、自然とあんが溶けて、

水分が減って、鍋の中身がどんどん少なくなると同時に粘りが出てきて、

最終的には混ぜる早さも早くなり、鍋の底が見えるようになるまで煮込んでいきます。

煮込んだあとはすぐに火からはずしますが、余熱でグツグツと泡立ってます。

冷めないうちに、ご主人特注の充填するための容器に移し替えて、

容器に充填していきます。見た目簡単そうにも見えますが、この作業を先代のお母様からやらせてもらえるまでに2年かかったとのこと。
このあと容器にいれたまま冷やし、封をして包装して完成!
↓↓↓

このように全ての工程を手作業でようかんづくりをしている所はほとんどないとのことで、やつだ屋のご主人は貴重な存在であると改めて感じた。
何でも効率化や大量生産のために機械を導入して作るのが主流となっている中、この技を残していって頂きたいと思ったし、残す手伝いが出来ればともおもった。
そのほかで驚きなのが、ようかんづくりに使用している道具や設備などは、ほとんどご主人が手作りで作られているとのこと。
欲しいものを作ったり、既存のものを改良したり、試行錯誤しながら「とにかくやってみる」という姿勢でいろんなことにチャレンジされている姿勢もとても素晴らしいと感じた。
私もこんな風に年を重ねていければと思った。
(コーヒーようかんの食レポは別の投稿でご紹介します。)

↑あんを入れた直後はこんな感じですが、

煮込みながら混ぜていくと、自然とあんが溶けて、

水分が減って、鍋の中身がどんどん少なくなると同時に粘りが出てきて、

最終的には混ぜる早さも早くなり、鍋の底が見えるようになるまで煮込んでいきます。

煮込んだあとはすぐに火からはずしますが、余熱でグツグツと泡立ってます。

冷めないうちに、ご主人特注の充填するための容器に移し替えて、

容器に充填していきます。見た目簡単そうにも見えますが、この作業を先代のお母様からやらせてもらえるまでに2年かかったとのこと。
このあと容器にいれたまま冷やし、封をして包装して完成!
↓↓↓
このように全ての工程を手作業でようかんづくりをしている所はほとんどないとのことで、やつだ屋のご主人は貴重な存在であると改めて感じた。
何でも効率化や大量生産のために機械を導入して作るのが主流となっている中、この技を残していって頂きたいと思ったし、残す手伝いが出来ればともおもった。
そのほかで驚きなのが、ようかんづくりに使用している道具や設備などは、ほとんどご主人が手作りで作られているとのこと。
欲しいものを作ったり、既存のものを改良したり、試行錯誤しながら「とにかくやってみる」という姿勢でいろんなことにチャレンジされている姿勢もとても素晴らしいと感じた。
私もこんな風に年を重ねていければと思った。
(コーヒーようかんの食レポは別の投稿でご紹介します。)
2015年11月12日
【見学レポート】コーヒーようかん(やつだ屋)<1>

今日は、あんこ部創立以来初の工場見学に行ってまいりました。
以前の投稿で「柿ようかん」を紹介させていただきましたが、その製造者でもありますやつだ屋さんに、あんこ部員のがきたかと小豆さんの二人でお邪魔して製造風景を見学させていただきました。
佐賀の市街地から北の方の山あいに位置する温泉地「古湯」の温泉街に店舗と工場を構えて営業されている。
今のご主人のご祖父様が初代で始められた菓子店を、ご主人のお母様が二代目として引き継ぎ、現在ご主人が三代目として製造・販売をされている。
ご主人は若かりし頃に脱サラをして地元に戻り、家業を引き継ぎ、この道に入って今年で37年とのこと。
店舗の奥の狭い通路を入っていたところが作業場で、ご主人が一人で作業するにはジャストサイズとも言える広さ。本日2名でお伺いしたのだが、若干ご迷惑をおかけした感があるほどこじんまりとしている。
やつだ屋さんのようかんは、栗、茶、柿、コーヒーの4種あるのだが、本日は「コーヒーようかん」を製造されるところを見学させていただいた。

こじんまりとした作業場では、コーヒーをドリップするためのお湯がやかんで沸かされており、その水は店舗の向かいで営業されている「英龍温泉」の温泉水を使っているとのことで、ご主人がわざわざ製造のたびに汲みにいっているそうだ。

お湯が沸くと、ご主人の手作りという業務用(?)のオリジナルドリッパーが登場!豪快にやかんから注がれた温泉水でコーヒーが抽出され、コーヒーの良い香りが作業場を包み込みました。

その後、水で戻した寒天を投入し、丁寧にアクをとってから、グラニュー糖と上白糖を投入し、さらにあんを投入。

焦げ付かないようにご主人が専用の混ぜ棒でゆっくりと鍋の中身を混ぜていく。
煮立ってくると鍋の縁ギリギリのところまで泡立ち、火加減を調整したり、混ぜ棒で上手に使って、泡立った表面が吹きこぼれないようにひたすら混ぜていく。
(つづきは、また明日投稿します。)